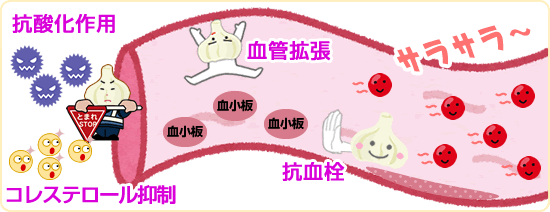
血液サラサラ効果はにんにくの代表的な効能です。ニンニクの効能と言うと体力増強や滋養強壮などのイメージが強いですが、血栓を抑制し、血流を促進する血液サラサラ効果も医療や栄養学分野の方にはよく知られた効能です。
血液サラサラの何が健康に良いのか?
血液がサラサラして血流が良いと体の隅々まで栄養を供給することができ、更に体の不廃物や毒素などを排出しやすくなります。それにより新陳代謝が活発になり、健康で若々しい生活をおくることができるようになります。逆に血液がドロドロしていると病気がちになったり老化が進行します。
しかし、「血液サラサラ」とは本来正常な血流の状態であり特別なことではありません。わざわざ「血液サラサラ」という言葉が使われるようになったのは近年、血液がドロドロになる人が増えてきたからです。
血液がドロドロになる要因は、偏った食事や不規則な生活、運動不足、ストレスなどの生活習慣にあります。これは生活習慣病の要因でもあります。
生活習慣病には主に「高血圧」「糖尿病」「脂質異常症」「肥満」などがありますが、これらの病気になると血液がドロドロしてきて、動脈硬化を進行させる原因となります。動脈硬化が進行すると心筋梗塞や脳梗塞の危険性が高まり、ひどい場合は死に至ります。
生活習慣病を根本的に治療するには、規則正しい生活や食事制限、そして適度な運動など生活習慣を改める必要がありますが、最も気を付けなければいけないのは動脈硬化の進行です。
それには血液ドロドロの状態を改善する必要があります。その時に有効なのが血液サラサラ効果なのです。
つまり血液ドロドロになりがちな現代人にとって、血液サラサラ効果とは健康や美容を促進する要因となり、特に生活習慣病における動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞の危険性を軽減させる作用もあるのです。
実際に地中海地方の人に心臓血管疾患が少ないのはにんにくを多く食べるからと言われています。
血液がドロドロになる要因
血液ドロドロの間接的な要因は前述した生活習慣や水分不足といったものがあります。例えば、現代の食事は中性脂肪やコレステロールを含む食品が多いので、食事に気を付けないと血管内に脂質が溜まりやすくなります。また、運動不足や水分不足は血行を悪くし、血液の濃度を高めます。更にストレスや食品添加物の摂取は活性酸素を発生させる要因となり、血管内に過酸化脂質を作り出します。
血液がドロドロになる直接の要因は主に「悪玉コレステロール(LDLコレステロール)」「中性脂肪」「活性酸素」そして「血栓」です。
偏食などにより分解・排出しきれなかった中性脂肪や悪玉コレステロールが血管内に付着し、それに活性酸素が結合すると過酸化脂質という固い塊(プラーク)になります。過酸化脂質が増えると血管が詰まって血管が破れます。そうすると血栓が作られ血管の傷を塞ごうとします。
この状況が頻繁に起こると血管内に血栓が大量に発生し、今度はその血栓で血管が詰まって破れ、更に血栓ができやすくなるという悪循環になり血液がドロドロになるのです。
にんにくの血液サラサラ効果の仕組み
にんにくには血液をサラサラにする効能がいくつかあります。具体的には次のようなものです。
- 抗血栓作用(血小板凝集抑制作用)
- コレステロール抑制作用
- 抗酸化作用
- 血管拡張作用
抗血栓作用(血小板凝集抑制作用)
抗血栓作用はにんにくの効能の中でも強力な作用を持つもので、医学的には血小板凝集抑制作用と言われています。
血栓は血小板が凝集する(集まり固まる)ことでできますが、にんにくが含まれるアリインが調理過程で変化するジアリルジスルフィド(DADS)、アリルメチルスルフィド(AMS)、メチルアリルトリスルフィド(MATS)、ジメチルトリスルフィド、アホエン、ビニルジチインなどのイオウ化合物には血小板の凝集を抑制し血栓をできにくくする効能があります。
この抗血栓作用により血管が詰まりにくくなるため血液ドロドロの悪循環を抑制し、血液サラサラを促進することを期待できます。
コレステロール抑制作用
効果性を懐疑的とする研究報告もありますが、にんにくにはコレステロールを抑制する効能があるとされます。
にんにくのコレステロール抑制作用は「コレステロールの生成を抑制する」という面と「コレステロールを低下させる」という2つの面があると言われています。
にんにくから発生するS-アリルシステイン、アホエン、ビニルジチインといった成分には、HMG‐CoA合成酵素及びHMG‐CoA還元酵素といったコレステロール合成に必要な補酵素の働きを妨げることによってコレステロールの生成を抑制する効能があると考えられています。
また、同様ににんにくのアリシンが変化してできるジアリルジスルフィドやジアリルトリスルフィドといったスルフィド類には、肝臓内に貯蔵されたコレステロールを胆汁へ排出するのを促進させる効能があるとされ、血中のコレステロール値を低下させると考えられています。
これらの効能により血管内にコレステロールが溜まるのを防ぐことで血液サラサラ効果を期待することができます。
抗酸化作用
血液がドロドロになる要因の一つに活性酸素があります。実はコレステロールだけであれば、血管内にあってもそれほど危険性はありませんが、コレステロールに活性酸素が結びつくと過酸化脂質という危険な物質に変化するのです。
過酸化脂質は血管にこびれ付き血管を固くすると共に溜まって血管を狭くします。そうなると血管が狭くなり血流が滞ることで血液がドロドロしやすくなってきます。また血管に傷がつきやすくなり、血栓を発生させる要因となり血液ドロドロを促進させます。
にんにくに含まれるビタミンE(アルファトコフェノール)は活性酸素を除去する抗酸化作用があることで知られていますが、同様にニンニクに含まれるイオウ化合物にも抗酸化作用があると考えられています。
これらにんにくの抗酸化作用が過酸化脂質を抑制し、血液サラサラにつながると考えられます。
血管拡張作用
血管に弾力性があると多少血液がドロドロしていても血流を促進することができます。
にんにくには血管を拡張させることで血流を促進する作用があると言われます。にんにくの血管拡張作用の仕組みはハッキリとは解明されていませんが、にんにくに含まれるイオウ化合物の一部が赤血球と交わることにより硫化水素が発生し、血管を構成する平滑筋を弛緩させて血管が広がると考えられています。
またにんにくに含まれるスコルジニンやアデノシンにも血管を広げる効能があると考えられています。これらニンニクの血管拡張作用により血流が促進され血液サラサラ効果が期待できるのです。
血液サラサラ効果の注意点
にんにくの血液サラサラ効果は動脈硬化や心筋梗塞や脳梗塞のリスクを軽減する働きが期待できますが、注意しなければいけない点もあります。
血流が良くなったり、血栓ができにくくなるということは血管が破れた時、血が止まりにくくなるということでもあります。
基本的に食事でにんにくを食べる範囲ではこのようなことを心配する必要はありませんが、手術や出産前のにんにく摂取は避けた方が良さそうです。
また、血液凝固系の障害がある人やアスピリンなど抗血小板作用のある薬を使用している人は医師や薬剤師に相談してからにんにくを食べた方が良いです。